広告
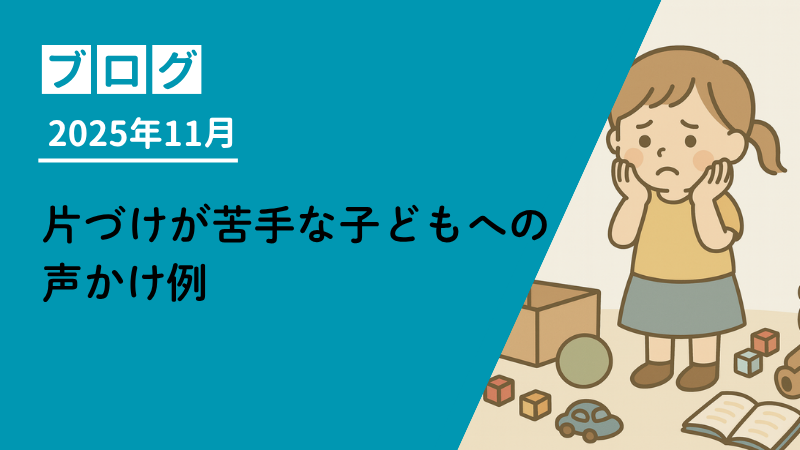
子どもの片づけが進まない…。
声をかけても動かない…。
怒らないようにしたいのに、ついイライラしてしまう…。
そんな悩みを持つご家庭はとても多いです。
実は、子どもが片づけられない背景には「脳の特性」や「発達特性」が深く関係していることがあります。
この記事では、
発達障害・グレーゾーン・特性のある子どもに向けて、
今日から使える「片づけの声かけ例」を、特性ごとに詳しく紹介します。
発達特性がある子が片づけにくい理由
発達障害(ADHD・ASDなど)やグレーゾーンの子どもは、
片づけに必要な以下の力が苦手な場合があります。
- 注意の切り替え
- 作業の見通し
- ワーキングメモリ(覚えておく力)
- 計画性
- 判断(選ぶ・捨てる)
- 感覚過敏/鈍麻
- 先延ばし
- 過集中とストップの難しさ
つまり、「やりたくない」のではなく、脳の特性として難しいのです。
声かけを変えるだけで、子どもの行動は大きく変わります。
子どもへの声かけがうまくいく「3つのポイント」
① 抽象的ではなく“具体的”に伝える
「ちゃんとして」「片づけて」「全部しまって」などの抽象的な指示は、多くの子どもにとってイメージが曖昧で、何をどうすればいいのか分かりづらい表現です。
特に、発達障害(ADHD・ASD)やグレーゾーンの子どもは、言語の処理が苦手/イメージ化が苦手/複数の作業を同時に捉えにくいという特性があります。
そのため、「どの場所を」「何を」「どうするか」を具体的に伝えると、子どもが“行動できるレベル”までタスクが明確になります。
【例】
×「ちゃんと片づけて」
〇「床にあるブロックを、この青い箱に入れてね」
→ これだけで、行動する確率が一気に上がります。
② 選択肢を与える
人は「命令される」よりも「自分で選んだ」方が動きやすくなります。
これは大人も子どもも同じで、脳科学の研究でも、自己決定感が行動力を高めると分かっています。
特に発達特性のある子は、
- 「やらされ感」で反発しやすい
- 主導権が奪われると不安が高まり動けない
- 選択肢があると安心しやすい
という傾向があります。
だからこそ、「どっちがいい?」の二択がとても効果的です。
【例】
「ブロックから片づける?それとも本からにする?」
→ 選択肢を与えることで、親子バトルが減り、子どもの主体性が育ちます。
③ 行動を細かく分ける
片づけは、大人が思う以上に多くの作業工程が必要な「複雑なタスク」です。
特に以下の力をフルに使います:
- 注意の切り替え
- ワーキングメモリ
- 物の分類
- 判断
- 手順の理解
これらは 発達障害の子どもが最も苦手としやすい領域です。
そのため、一気に全部やろうとすると「どこから手をつけていいか分からない」という状態になりがちです。
そこで、1個だけ・3分だけ・この箱だけなど、行動のハードルを下げる「タスク分解」が必要になります。
【例】
「まず、この3つだけ片づけてみようか」
「最初の1個だけでOKだよ」
→ 成功体験が積み重なると、片づけは確実に進みます。
子どもが片づけられなくなる「NG声かけ」とは?
片づけが苦手な子どもに、ついやってしまいがちな声かけがあります。
悪気がなくても、実は脳の特性に合っていないため動けなくなる言い方です。
「やる気がない」「怠けている」のではなく、声のかけ方が負荷になっているだけの場合も多いので、ぜひ今日から一緒に改善していきましょう。
①「ちゃんとして」「片づけなさい」などの抽象的な指示
発達障害(ADHD・ASD)の子どもは
抽象語の理解が苦手/イメージ化が難しい特性があります。
「ちゃんと」が何を指すのか分からず、
“どう行動すればいいのか”が曖昧なまま。
→ 行動に移せず止まってしまう
▼改善例
「床にあるブロックを、この青い箱に入れてね」
「お皿をシンクに運んでね」
など、目的・場所・動作を具体的に伝える。
②「なんでできないの?」と理由を問い詰める
理由を聞かれると、
- “責められている”と感じて不安が高まる
- ワーキングメモリが弱い子は「自分でも分からない」
- 混乱してさらに動けなくなる
特に、子どもが片づけられない時にこの声かけをされると、自尊心が下がり、片づけ=イヤな時間になってしまいます。
▼改善例
「どうしたらやりやすいかな?」
「一緒にできるところ探そうか」
→ 解決にフォーカスした声かけに。
③「早くしなさい」「なんでまだやってないの」
“早く”という曖昧なスピード感は、特性のある子には伝わりにくいです。
プレッシャーが強くなるほど、脳は動きづらくなります。
特にADHDの子は
焦り→混乱→手が止まる
というループに入りやすいです。
▼改善例
「タイマー3分だけやってみようか」
「この3つだけ片づけたらOK」
→ 数値化・具体化が効果抜群。
④「全部片づけて」など、量を把握できない指示
“全部”の範囲が広すぎて、脳の負荷が一気に上がります。
発達障害の子は、
- 作業の見通し
- タスクの優先順位
をつけるのが苦手。
そのため、「どこから手をつけたらいいか分からない」状態に陥り、動けません。
▼改善例
「今日はここだけやろう」
「まず5個だけでいいよ」
→ 量を“見える単位”にすると成功率が上がります。
⑤「どうして散らかすの?」「まだできてないの?」と比較・批判
否定的な言葉は、脳の“逃避モード”を強化します。
子どもは「怒られるからやる」という状態になり、片づけが続かず、意欲も育ちません。
特にASDの子は自己否定に敏感で、批判が多いと行動量が極端に減る傾向があります。
▼改善例
「ここまでできたね!」
「次はどれ片づける?」
→ 小さな成功の積み上げが効果的。
【特性別】片づけが苦手な子どもへの声かけ
① 注意が散りやすい子
「今は“ここだけ”片づけようね」
「この3つだけ入れてみよう」
「タイマー3分だけ一緒にやろうか」
「順番はこれだよ(写真を見せる)」
「まず1つだけ手に取ってみて」
② 切り替えが苦手な子
「あと2分で片づけはじめるよ」
「この遊びが終わったらにしようね」
「最後に1個だけお片づけしよう」
「片づけゲームにしちゃおう!」
③ ワーキングメモリが弱い子(覚えておけない)
「次はこれだけだよ」
「やることは“2つだけ”」
「同じ写真のところに置いてみて」
「一緒に見ながらやろうね」
④判断が苦手・迷って動けない子
「残す?捨てる?他の方法はある?」
「今日1番大事なのはどれ?」
「ベスト3だけ残そうか」
「“使ってる/使ってない”で分けてみよう」
⑤ 感覚過敏・感覚鈍麻がある子
「ザラザラ嫌なら手袋つけて片づけよっか」
「見えるものが多いと疲れちゃうから隠そう」
「ここは静かな場所でやろう」
⑥ やる気が出ない・先延ばしする子
「5秒だけ動いてみよっか」
「一緒に最初の1つだけやろう」
「ここまでできたね!すごいよ」
「終わったらお茶にしよう」
⑦ こだわり・固執が強い子
「これ、大事なんだね」
「安全な場所に置ける方法を一緒に考えよう」
「順番を変えないまま片づけようか」
⑧ 位置が覚えられない子(空間認識が苦手)
「青いシールの箱が“本”の場所だよ」
「写真と同じ位置に置いてみよう」
「マットの上に置くとわかりやすいよ」
⑨ 不安が強い・怒られたくない子
「間違っても大丈夫だよ」
「今日は全部じゃなくていいよ」
「ゆっくりでOKだよ」
⑩ やめ時がわからない子(過集中しやすい)
「タイマー鳴ったら終了ね」
「ここまでできたらおしまい」
「最後に1個片づけて終わり!」
声かけだけじゃない!片づけがラクになる「環境づくりのコツ」
声かけだけではなく、環境を整えると成功率が一気に上がります。
- 見える収納(透明ケース・色分け)
- ラベルや写真で視覚化
- “保留ボックス”で判断の負荷を下げる
- スマートタグで「探す」を減らす
- 量を減らして“選ばなくてよい環境”に
特性のある子は、環境に助けてもらうことが得意です。
声かけを変えれば、片づけは必ずラクになる
片づけは、「やる気」や「性格」の問題ではありません。
脳の特性+環境の組み合わせです。
だからこそ、子どもが動ける声かけを使うと、劇的に行動が変わります。
子どもが片づけられない時、責める必要はありません。
今日紹介した声かけから、まず1つでいいので試してみてください。
小さな成功体験の積み重ねが、子どもの“できる!”を育てます。

ライフオーガナイザー®として、特にADHD傾向のある方や片づけが苦手な方をサポート。完璧主義や罪悪感、思い込みなど、片づけの障害となる心理的要因に寄り添い、無理なく続けられる仕組みづくりを提案しています。
2012年からこの分野を学び、2023年にアメリカの専門団体「Institute for Challenging Disorganization®」にて日本人初のCPO-CDを取得。
「片づけの負担を減らし、自分らしい人生を楽しめる人を増やしたい」との思いで活動中。